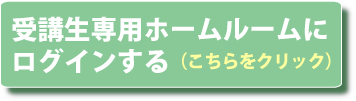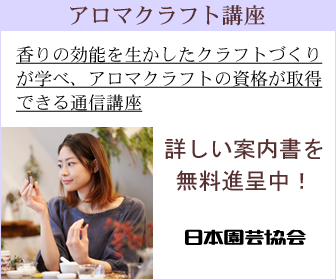ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.84
精油を原液で使ってよいものでしょうか?
2月に入っても厳しい寒さはまだまだ続きますが、暦の上では「節分」「立春」と春のささやきが聞こえて来ました。立春は冬至と春分の中間にあたり、茶摘み歌で歌われる「八十八夜」の起算日(第1日目)でもあります。立春から春分の間に、その年の初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風が「春一番」です。まだまだ寒い、北国では積雪と闘う時期ではありますが、春を待つ、春を迎えることのわくわくする気持ちは抑えられません。皆さまも、まわりの春を探してみてはいかがでしょうか。
さて、最近「精油(エッセンシャルオイル)の原液使用」が話題になっており、「精油を原液で使っても大丈夫か?」というお問い合わせが何件も寄せられています。もちろん答えは「No」ですが、そうした単純な回答ではご納得いただけず、使い方や、使えない理由など、もう一歩突っ込んだ知識が求められることもしばしばあります。

|
「アロマテラピー」という言葉が日本で聞かれるようになったのは、ロバート・ティスランド氏の『The Art of Aromatherapy』(1977年刊)という本が邦題『アロマテラピー<芳香療法>の理論と実際』(1985年、フレグランスジャーナル社刊)として日本で出版されたことがきっかけでしょう。
40年以上も前のことですが、この本の中で既にロバート氏は「精油を多く用いれば、いっそう体調がよくなるのではないかとか、結果がもっと早く出るだろうとかと考えてはいけません」(*1)と述べています。この本の内容はロバート氏自身の研究と実践によるものですが、フランスの医師ジャン・バルネ氏やパオロ・ロベスティ氏をはじめ、過去の多くの薬草研究家の研究成果が反映されています。
*1:『アロマテラピー<芳香療法>の理論と実際』(1985年、フレグランスジャーナル社)より
消費者や環境に対して、安全性の高い香粧品(化粧品や香料など)の供給に専念することを目的に設立された「IFRA(国際香粧品香料協会)」という国際組織があります。IFRAでは香料素材の安全性のガイドライン(IFRAスタンダード)が設けられ、その中に精油(天然香料)も含まれています(*2)。
IFRAは長年にわたり、皮膚感作性(皮膚に接触することでアレルギー反応を起こす性質)により人体に有害となる可能性のある天然物質および合成物質を特定して、データベースを構築し、香粧品の安全性を監視、評価しています。その基準に対しては賛否両論がありますが、ひとつの大きな目安となります
*2:2025年1月現在、IFRAスタンダードはEUの法規制に吸収されています。
公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)は、精油の希釈濃度は「ボディに使用する場合は1%以下、フェイスに使用する場合は、0.1~0.5%以下」(*3)というガイドラインを出しています。これはあくまでも目安で、体質、体調、肌質に個人差があることを配慮することも付け加えています。
なぜ「1%」以下としているのか、そのひとつの参考資料としてIFRAのガイドラインがあります。IFRAの基準には1%を超えるものもあれば、1%以下のものもあり、大変複雑です。AEAJでは、一般の人への分かりやすさを考慮し、1%以下と設定しました。ですから、必ずしも1%までなら絶対に安全であるとか、誰にでも安全というものではありません。
*3:公益社団法人日本アロマ環境協会発行『アロマテラピー検定公式テキスト1級・2級』より

|
このように、さまざまな基準を見ても、精油を原液で使用することのガイドラインは見当たりません。一部の書籍などの中には、原液で使用する処方が掲載されている場合もありますが、医療の専門家が治療のために使う場合を除き、原液で使うことの利点は見つかりません。
精油は植物中に存在する芳香成分が高濃度に含有されたもので、原液で使用することによる皮膚の炎症反応なども報告されています。実際に、精油の原液が誤って手についてしまい、肌が赤くなったり、かゆくなったり、水泡ができたりした経験は私にもあります。
また、精油に対するアレルギー反応の報告も、原液で使用してしまった場合の方が多くあります。アレルギーは、その物質が一度でも人体にアレルゲンとみなされてしまうと、二度とその精油を使うことができなくなる可能性があります。
原液使用のリスクが多いのに対して、利点の例が少ないと考えられます。あえて危険を冒す必要があるでしょうか。
また、精油の用途として食品の香り付けや医薬品がありますが、医師、薬剤師や専門業者の処方によって行われており、その希釈濃度も極めて低い場合がほとんどです。
アロマテラピーや精油の安全性などについては、常に最新の情報をキャッチし、学び続けることが大切です。私の手持ちのガイドブックなどでも、古いものは発行当時の基準で示されたものもあり、戸惑うことがあります。海外のセラピストによって書かれた良質な本もありますが、情報のアップデートは必須です。情報過多の時代、周囲に溢れる情報に流されないことは、アロマテラピーも一般情報も同様かと思います。
風邪やインフルエンザなども流行っています。どうぞご自愛の上、明るく春を迎えられますようお祈りします。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◆このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。