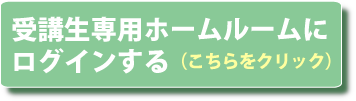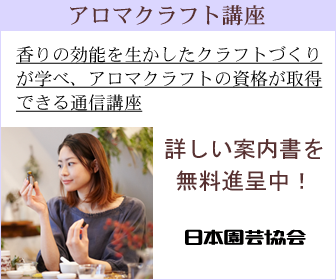ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.81
追悼 熊井明子先生を偲んで
まだまだ厳しい暑さの残っていた9月、作家、エッセイストでポプリ研究家の熊井明子先生が旅立たれました。先生は数々の功績をお持ちですが、私たちハーブ、アロマ、植物好きへの最大のギフトは、日本に「ポプリ(*1)」を紹介してくださったことでしょうか。
*1:ポプリとは花やハーブ、精油などの香料を混ぜあわせ、容器に入れて熟成させたもの。ポプリの歴史や詳しい作り方に興味のある方は、日本園芸協会の「ハーブコーディネーター養成講座」「アロマクラフト講座」にて紹介しておりますのでご参考になさってください。

|
先生がポプリに出会ったのは、10代の頃に愛読されていた『赤毛のアン』(*2)シリーズでした。文中に登場する「雑香(ざっこう)」と訳されたものが気になり、原書などを調べ、確認したそうです。原書では「pot-pourri」と記されており、その作り方を含め、室内での香りの楽しみ方などをその後も調べ続ける一方で、各種の花やハーブとオイル(香料)で作られたこの雑香に「ポプリ」という原語の発音に最も近い言葉を見つけ出し、命名しました。それまでは「ポットポーリ」「ポプリン」など、名称はバラバラで呼ばれていましたが、「ポプリ」として市民権を得ました。これらの成果は『愛のポプリ』(*3)というエッセイ集にまとめられて発刊されます。
*2:『赤毛のアン』カナダの作家Ⅼ.Ⅿ.モンゴメリ著。
*3:『愛のポプリ』講談社刊、1980年。

|
熊井先生は映画監督の故・熊井啓氏の妻でもあります。1978年「徹子の部屋」に出演しポプリを紹介すると、マスコミに注目され、関心を持つ方が急増しました。カルチャーセンターの依頼で、ポプリの作り方を教える講座を開講することにもなります。さらには全国から届く要望に応えるために、ポプリを教える講師を増やすことを考えられました。そこで誕生したのが「ポプリ講師養成講座」です。素材の話、産地の話、香りにまつわる文学や絵画、音楽、先生の幅広い教養と知識に魅了され、受講生の中には1年間修了の講座を毎年受講し続ける方もいらしたそうです。ポプリ講師という肩書を元に、講師として社会的に自立することも先生は熱心にすすめました。卒業生は全国で講座を開き、ポプリの普及に拍車がかかります。この講座は20年以上続き、卒業生の中には今なお活躍されている方も少なくありません。
先生は、北海道・中富良野のラベンダー農園「ファーム富田」の創設者である富田忠雄氏とも親交が深く、富田氏がまだ細々とラベンダー生産を続けていた頃に、ラベンダーをサシェ(匂い袋)にすることをアドバイスされたそうです。また、富田氏のみならず、富良野エリアで香料会社が撤退後もラベンダー生産を続けた方たちを訪問し、その功績をインタビューされるなど、国内外の情報収集にとても熱心に活動されました。

|
ラベンダーだけでなく、和種ハッカからとる薄荷脳(はっかのう:vol.79で紹介)なども、その存在を早い時期から紹介されました。先生を通じ、私たちは見たことも聞いたこともないハーブ、香木や香料をたくさん教えていただきました。
精油も同様です。ポプリの香りを補強する香料は、当時も今も合成のものがほとんどですが、先生は当初から天然香料をすすめていました。いわゆるエッセンシャルオイル(精油)です。80年代前半の日本では、まだほとんど入手が難しいだけでなく、蒸留などの特別な方法でハーブから香料を抽出することができることや、そもそもその存在すら知られていませんでした。ロバート・ティスランド氏のアロマテラピーが日本に紹介されるずっと前です。
単に「ポプリの作り方」というHOW TOを伝えようとするだけでなく、「今の生活をより充実させて楽しく生きるために、さまざまな香りをさまざまな方法で取り入れましょう」という思想を伝えることが先生のテーマでした。元明治薬科大学名誉教授の故・大槻真一郎氏の次の言葉が印象的です。
「熊井明子氏の功績は、薬草であるハーブを「楽しみ」として、一般の人たちにもわかるように魅力的に紹介したこと。ハーブがとても身近な存在になったことは、後々のハーブ文化の発展にとても貢献しています」
謹んでご冥福をお祈りします。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。