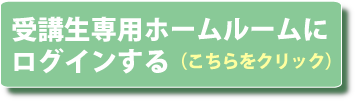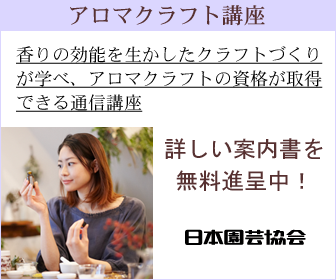ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.80
菊の香り
このたびの石川・能登地方の豪雨災害により、被害に遭われた皆様ならびにご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。また、救助活動に尽力されている全ての方々に深く感謝いたします。
本年元旦の能登半島地震でも大きな被害を受けた輪島市や珠洲市において、復旧に向けた取り組みが続く中での豪雨被害は、地域社会にとってさらなる困難をもたらしていることと存じます。被災地の皆様が一日も早く平穏な日常を取り戻されることを心より願っております。
さて、ヒガンバナ、キンモクセイ、ハギ等々、秋の花は数多くありますが、最も身近で、香り高いものは「菊の花」かもしれません。皇室の象徴やパスポートの紋章が「キク」なので、国花も「キク」だと思う人は少なくないかもしれませんが、調べてみると「キク」だけでなく「サクラ」も国花として扱われています。実は日本の国花は、公式に定められておらず、どちらも国を代表する花のようです。
キクは原産地の中国では仙境に咲く花とされ、不老長寿の薬として信仰されていました。日本へは奈良時代の終わり頃に、薬草として伝わったようです。しかし、その外観の美しさから宮廷や貴族にもてはやされ、庭に植えられたり、詩歌に詠われたりしたほか、紫式部の『源氏物語』にも登場します。

|
中国では奇数は縁起のよい「陽」の数とされており、最も大きい陽の数字「9」が重なる9月9日が「重陽(ちょうよう)」として五節句のひとつになっています。その風習が日本にも伝わり、平安時代には「重陽の節会(せちえ)」が宮中で行われるようになりました。菊の香りを移した菊酒を飲むなどして、邪気を払い長命を願う習慣も中国から伝わったものです。

|
また、「菊の被綿(キセワタ)」という習慣もあります。重陽の節句の前日である8日に菊の花に真綿(*)を被せ、夜露と花の香りを移しとります。そして翌日の重陽の節句の朝にその綿でからだを拭い清めると、老いを遠ざけ、長寿を保つと信じられていました。被綿は『紫式部日記』をはじめ『枕草子』などの古典文学にも登場します。とても興味深い習慣で、来年はぜひチャレンジしてみたいと思います。
*真綿(まわた)とは、蚕(かいこ)の繭を煮た物を引き伸ばして綿にした物。日本では室町時代に木綿(もめん)の生産が始まる以前は、綿(わた)ということばは、真綿を指しました。

|
数多くの品種がある菊の中でも、特に香りがよく、花弁に苦みが少ない品種は、食用菊として栽培されており、茹でてお浸しにしたり、酢の物などに用いられます。
また、Chrysanthemum morifoliumの花が「菊花(きくか)」の名で生薬として日本薬局方に掲載されています。ルテオリン(フラボノイド)などの成分を含んでおり、解熱、解毒、消炎などの作用があるとされています。風邪を引き起こす「風邪(ふうじゃ)」を除き、風邪による頭痛や目の充血などに効果があり、これからの季節に役立ちます。クコやサンザシ、ナツメなどとブレンドすると目の働きを回復させたり血圧を下げたりするなどの相乗効果が期待できます。
ハーブにもキク科のものはたくさんあります。ジャーマンカモマイル、ローマンカモマイル、フィーバーフュー、エキナセア、コルツフット、タンポポ、バードック、カレンデュラ、ヤロー等です。科別にハーブや精油を眺めてみるのも楽しいですね。
旧暦の9月9日は、今年(2024年)は10月11日にあたります。本来は旧暦で楽しむ行事ですので、あらためて重陽の節句、私も楽しみたいと思います。
作家・エッセイストの熊井明子先生が、9月21日ご逝去されました。熊井先生は日本にハーブ、ポプリの楽しみを紹介された方で、アロマテラピーの発展にも多大なる貢献をいただきました。ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。