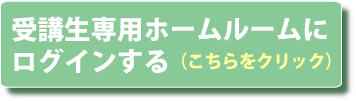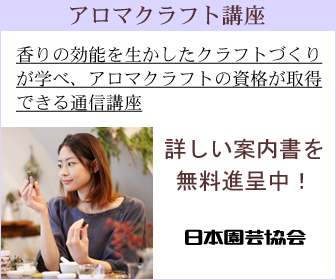ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.77
夏の甘い健康法
なんとなく普段よりだるかったり、なんだか不調だったりと、最近は猛暑ということもあり、夏の不快感をいっそう強く感じる方も多いことでしょう。昨今の気候変化は私たちの適応可能な範囲を超えているように思えます。
漢方の源流である中医学の考え方では、気候そのものが病気の原因=「邪気」となると考え、夏に多汗(たかん)、口渇(こうかつ)、脱力感、手足の倦怠感(けんたいかん)、吐き気、下痢などが起こりやすいのは、「暑邪(しょじゃ)」と「湿邪(しつじゃ)」のためと考えます。普段よりまめに水分を補給する、消化のよいものを食べる、体を冷やさないようにする、などが夏の養生になります。
私の身近なところでは、スリランカのアーユルヴェーダやイランのイブン=シーナの教えなど、古くから伝わる伝統療法には、現代にも通ずる、季節の過ごし方の教えがあります。

|
6月が終わり、1年の半分が過ぎたことになりますが、神事では6月30日に「夏越の祓(なごしのはらえ)」があり、半年間の厄を落とし、後半の無病息災を祈願します。これにちなんだお菓子が「水無月(みなづき)」です。京都発祥で、6月になると店頭に並びますが、最近は関東地方でも見かけるようになりました。「水無月」には歴史的な背景がありますが、このお菓子に使われている「小豆(アズキ)」には、まさに夏の体調管理にぴったりの効用があります。

|

|
アズキの歴史は古く、縄文時代の遺跡からアズキの種子が出土しており、『古事記』や『日本書紀』では死と再生の象徴としてアズキが登場します。栄養価も高く、昔は「薬」として用いられて来ました。また、アズキの持つ「赤色」は、邪気を払う呪力があると信じられていたため、小正月には「小豆粥」を食べたり、祝い事に「お赤飯」を炊いたりという風習も生まれ、今でも続いています。

|

|
江戸時代、白米を食べるようになった江戸で「脚気(かっけ)」が流行した時には、ビタミンB1補給のためにアズキを食べたそうです。アズキにはポリフェノールが豊富に含まれ、活性酸素の除去に役立ち、全身の老化防止になるそうです。活性酸素は日々蓄積されるため、ポリフェノールも一度にたくさん摂るのではなく、少しずつ、毎日食べるのが効果的です。たとえばゆでアズキなどにして、毎日の朝食に取り入れるとよいでしょう。
また、アズキは腸内細菌を元気にするプレバイオティクスを含み、小腸の免疫機能を活性化する効果があります。不溶性食物繊維をごぼうの3倍も含み、大腸の有害物質を吸着して排泄する効果も期待できるため、腸内環境の改善にも活躍します。
「脳腸相関」と言って、脳と腸は深い関係でつながっているという研究が進んでいます。お腹の調子を整えることが脳の疲れを癒し、自律神経のバランスを整えることにもつながります。夏のストレス解消法のひとつに、アズキのスイーツを取り入れてみるのもよいかもしれません。ただし、糖分の摂り過ぎにならないようお砂糖は控え目にしましょう。少し手はかかりますが、アズキのお茶などもおすすめです。自分に合った方法で、しなやかに夏を乗り切りましょう。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。