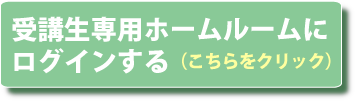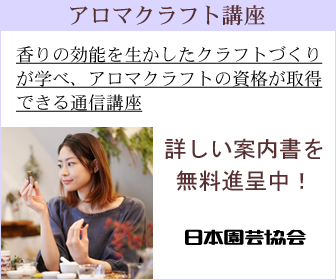ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.75
レモングラスあれこれ
5月5日の「端午の節句」に菖蒲湯を楽しまれた方も多いと思います。ショウブはアヤメ科のハナショウブとは別種で、根は漢方薬にも使われます。旧暦の5月5日は、現在の暦では6月の梅雨の時期にあたりますが、季節の変わり目で体調を崩しやすく、それを「邪気(じゃき)」によるものと捉え、それに対応した養生を奨励するのは、理にかなった風習と言えるでしょう。
さて、最近は国産ハーブの製品化が全国で進められていますが、そのひとつにレモングラスがあります。イネ科で生育環境が日本の気候風土にも合い、育てやすいハーブです。国産ハーブと言うと、生産量や人件費の問題で比較的高単価になることが多く、市場には並びにくかったのですが、コロナ禍を経て消費者の価値観も変わり、価格より安全性が重視されるようになりました。生産者の顔が見えて安心できる商品への人気は、ハーブやアロマなどでも高まってきたようです。
原産は熱帯アジアとされ、その代表はタイです。「タイはレモングラスの最大の生産地であり、最大の消費国」とタイ人自身が語るほど、レモングラスはタイの食生活には欠かせません。日本料理で言えばダシをとるように、フランス料理ならブーケガルニのように、タイ料理ではレモングラスを使います。消化促進や毒消しのような効き目を期待して使うということもありますが、主たる目的はその香り、味のようです。肉や魚の臭みを消すほか、タイ料理独特の風味を生みます。またタイの自然療法に使うハーブボールにもレモングラスは欠かせず、そこでも「香り」をよくする効果が活用されています。

|

|

|
レモングラスと呼ばれるのは、世界中に50数種あると言うオガルカヤCymbopogon属の内、C. flexuosusとC. citratusの2種で、前者は東インド型、後者は西インド型として区別されています。東インド型は西インド型より繁殖力が強く、病害虫にも強いため、レモングラス精油の市場は東インド型が優勢のようです。
精油が持つ効能の中で代表的なのが、主要成分である「シトラール」に由来する抗菌性です。研究データでは、シナモンバーク、レモンユーカリ、クローブなどと並ぶほどの、細菌や真菌に対する強い抗菌活性が認められています。昆虫忌避に関しても、蚊に対しての中程度の忌避作用、イエバエの殺虫作用などがあります。また、マクロファージの産生を抑制することで抗炎症作用を示すことも報告されています。
ただ、シトラールは一般には皮膚刺激が強く、アレルギー反応を起こしやすいとされており、皮膚刺激への注意は必要です。「香水への使用は0.7%以下にとどめる」という規制情報もあります。また、具体的な症例はないようですが、妊娠、分娩、授乳期のマッサージへの使用の禁忌がうたわれているのは、シトラールのエストロゲン様作用(女性ホルモンの様に働く)の可能性のためです。
レモングラス精油の効果的な活用法は、抗菌作用や防虫作用を活かすことです。肌への刺激を配慮すると、芳香浴もしくは、洗い流す石けんのような、肌に広範囲に精油を塗布したり、すり込むことのないものが向いているといえるでしょう。芳香浴で楽しむ場合も、香りが比較的強いため、低濃度にしたり、他の精油とブレンドするのがおすすめです。初夏から盛夏に向けて、おすすめの香りであり、ハーブですので、ぜひお楽しみください。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。