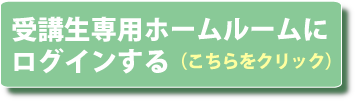ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.70
カンキツをマンキツする季節
春夏秋冬を楽しむ日本の暦には、半月ごとの季節の変化を示す二十四節気があり、それをさらに五日ごとに分け、気象の動きや花鳥風月の変化を知らせる七十二候があります。多くはその「兆し」を伝え、季節のうつろいを感じさせてくれます。ちょうど12月2日は「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」といわれ、そろそろ橘(柑橘類)の果実が黄色く色づき始める頃だと伝えてくれます。この暦は、元は古代中国で作られ、幾度も変更されながら今日にいたります。多くは古代中国で作られながら、私たちの現代の生活にもほぼほぼ即しているのは興味深いことです。身近に柑橘の木を見る環境がなくとも、収穫の時期を知ることができ、気がつけば、青果店には豊富な柑橘が並びます。

|
冬至も二十四節気のひとつで、ユズ湯に入る習慣はおなじみです。昼間の時間が最も短い日として、この日を境に新年とする信仰が日本や中国だけでなく、世界各地にあります。太陽を生命力の源とする思想も各地にありますが、特にケルト文化では、生命の再生の祝祭として冬至祭を祝いました。日本の風習として冬至にユズ湯に入るのは、いろいろな説がありますが、厄払いのための「禊(みそぎ)」の意味合いが強いようです。ユズは香りが強く、「強い香り=邪気を払う」という考えが由来とする説や、ユズは実がなるまでに17~18年という長い年月がかかるため、長年の苦労が実るように、という願いが込められているともいわれています。

|
果肉を食べるのではなく果汁の酸味や果皮の香りを楽しむ柑橘を「香酸(こうさん)柑橘」といいます。ユズ、スダチ、カボス、レモンなど、食の分野でも香りと酸味で料理を際立たせ、食欲を刺激する料理の名脇役で、柑橘系の精油の多くはこのグループです。柑橘というと果汁、果肉のイメージで、栄養学的にもビタミンCの供給源というイメージですが、「香り」の世界でも立役者で、果皮から得られる精油が多くのフレグランスに使われて来ました。歴史的には、インド原産の柑橘をヨーロッパに紹介したのはアレキサンダー大王とされていますが、彼が目をつけたのもその「香り」だったそうです。
ユズの香りには血行を促進し、肩こりや冷えを緩和したり、体を温め、風邪を予防する効果があります。精油は比較的高価ですが、果実そのものをお湯に浮かべても、アロマテラピー効果は十分期待できます。丸ごと使ってもよいですが、香りの成分を利用するには果肉や果汁より果皮が大事なので、果皮だけを削り取って使うのが効果的です。天然塩大さじ2に3~5滴の精油または果皮を刻んだものを加え、お湯に入れてよく混ぜます。ハチミツを加えれば、甘い香りが加わり、お肌がしっとりします。果皮はお湯に散らばるので、お茶用のパックなどに入れてください。精油も果皮も光毒性があり、皮膚刺激は強い方ですので、使いすぎには注意しましょう。

|
香りにはリフレッシュ作用もあります。柑橘類の豊富な季節でもありますから、鼻をクンクンさせながら果実を楽しんでください。少し早いですが、今年もお読みいただきありがとうございました。よいお年をお迎えください。お正月飾りを彩るのはダイダイです。これも柑橘ですね。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。
上から1番目と2番目の写真はphotolibrary の写真を使用。