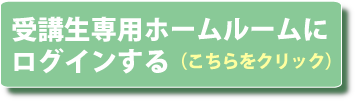ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.69
秋から冬の常備精油「ティートゥリー」
今年は開花がすっかり遅れたキンモクセイでしたが、お楽しみになられましたか? 私は友人から花をウォッカに漬けたものとシロップに仕立てたものをいただきました。雨の予報があったので収穫を急ぎ、花が高いところについているため枝ごと切り取って、そこから花を集めたなど、いざ収穫と言ってもいろいろと細かい苦労があることを友人の報告から実感しました。さっと洗い、乾かし、漬ける。何にでも共通しますが、手仕事に手軽なものはなく、丁寧に行うことに醍醐味があるのかと思います。

|
さて、気温が下がって来て空気が乾燥してくると、気になるのが風邪やインフルエンザの流行です。先日、私も今までに経験のないほどの痛みをノドに感じ、夜中に目が覚めました。応急手当にマヌカハニーを舐め、口の中、ノドに転がしたりして凌ぎましたが、感染症も疑われるので、総合病院で検査をしました。結果は陰性で大事には至りませんでしたが、予防の重要さ、日頃の健康管理、いざという時の応急手当の準備の必要性などを痛切に感じました。
また、マヌカハニーの癒しの効果も実感しています。マヌカハニーにはメチルグリオキサールという成分が含まれ、高い抗菌作用があります。蜂蜜なので、食品という安心感もあります。ハーブやアロマは楽しむためのものですが、救急にも活躍してくれます。
風邪やインフルエンザ対応で話題になる精油もいろいろありますが、一番効果が期待できるのは、ティートゥリーです。ユーカリと同様に、オーストラリアで伝統的に使われて来たハーブです。シドニーやメルボルンの町では、ドラッグストアや雑貨店にユーカリやティートゥリーの100ml入の精油の瓶などを見かけます。どう使うのか不思議に思いますが、それだけ日常生活になじんでいるということでしょうか。

|

|
ティートゥリーは先住民のアボリジニ族の万能薬でした。イギリスの探検家キャプテン・クックは彼らがお茶にして飲むのを見て、「ティー(茶)・トゥリ―(木)」としてヨーロッパに紹介しました。ティートゥリーが多く自生する地域は、小さな池や沼の集まる湿地帯で、そこは「Magical Lagoon(マジカルラグーン)」と呼ばれています。ラグーンにはティートゥリーのエキスが溶け込んでいると考えられ、先住民の女性たちはこの水に不思議な力があることを知っていました。子供がケガをしたり虫に刺された時水浴びをさせたり、出産の場として利用したそうです。風邪をひいた時は、ティートゥリーの葉をすりつぶして匂いを強く嗅いだり、お茶にして飲んだり、ラグーンはまさに森のクリニックのような場でした。今でもその湖畔にたたずむと、何とも言えない静けさに包まれ、とても静謐(せいひつ)な気持ちになります。

|
ティートゥリーは高い抗菌性を持ちながらも比較的刺激はおだやかで、多様な細菌に対し適応があることが使いやすいポイントです。ディフューザーで室内に香りを拡散させたり、ミツロウクリームなどを準備しておくとよいでしょう。刺激は穏やかですが、原液を肌につけたり、飲んだり、うがい水に垂らしたりという使い方は、おすすめできませんのでご注意ください。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。