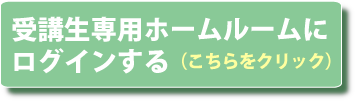ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.65
アロマと微生物の世界
食中毒が気になる季節です。食品を腐らせたり、食中毒をおこす原因は、細菌やカビといった微生物であることがほとんどです。微生物とは微小な生物全体の総称で、特定の生物をさす言葉ではありません。細菌、菌類(酵母、カビ、キノコなど)、微細藻類、原生動物など、いろいろな微生物がいます。微生物の増殖によって食べ物の成分が変質し、食べられなくなる状態を「腐敗」といいますが、同様に微生物によって成分が変質する場合でも、人間にとって有益な場合には「発酵」と呼ばれます。
食中毒はうれしくありませんが、発酵の世界はおいしく、面白く、大変興味深い世界です。味噌、醤油、チーズ、ヨーグルト、漬物、ビール、ワイン等々、私たちのまわりに発酵食品は数多く、地域柄、お国柄もあり、それを辿るのも楽しいです。特に日本はじめアジア圏はその気候から発酵に適した環境で、発酵食品の種類も豊富です。また、発酵は食品だけでなく、藍染などの染色や堆肥などにもそのプロセスが利用されています。私たちの暮らしは、想像以上に微生物に支えられているということでしょう。

|

|
微生物は人にも棲みつき、健康維持に貢献しています。健康な人の身体に日常的に存在する微生物(細菌)を常在菌と言います。人の場合、腸内に最も多く存在し、他に口腔内、皮膚表面などに棲息しており、様々な作用をもたらしています。乳酸菌やビフィズス菌、大腸菌なども常在菌の一種です。皮膚の常在菌が産生する脂肪酸で皮膚は弱酸性に保たれ、雑菌の定着を防いでいます。植物にも微生物は貢献します。その代表が、マメ科植物の根に共生する根粒菌(こんりゅうきん)です。根粒菌はその植物に窒素(肥料の三要素のひとつ)を固定します。
腐敗すると異臭がしたり、味噌やキノコによい香りがあるところからも、微生物と香りには密接な関係があることは簡単に想像できます。微生物には嗅覚器官がないにもかかわらず、匂いによって休眠状態から目覚めたり、成長を早めたり、匂いの情報が感知されていることがわかっています。例えば香木として昔から珍重される沈香(じんこう)は、沈香の木に生成されたテルペン類が、特殊な菌の作用で樹脂化したものとされています。微生物が芳香成分の生成を促進する例は他にも見られます。

|
逆に、植物の香り(精油)が微生物をコントロールすることも昔から知られ、ケガの治療やミイラづくりなどに活用されて来ました。精油の抗菌性研究の一人者、故井上重治先生は、抗菌性が強い精油として、シナモンバーク、タイム、オレガノを挙げています。注意しなければならないのは、私たちが日常生活で精油の抗菌力を期待して活用する場合は、その安全性も配慮しなければならないということです。抗菌性と安全性の両方から考えて、使いやすい精油として挙げられているのが、ティートゥリー精油ということになります。
「細菌」という言葉には抵抗を持つ方も多いかもしれませんが、奥深い「菌」の世界を覗いてみるのも面白いかもしれません。私はすっかりハマっております。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。
「(株)生活の木 提供」と表示がある以外の写真はphotolibrary の写真を使用。