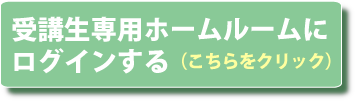ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.64
日本の石鹸製造のはじまり
好きな香りは? という問いに「石鹸の香り」という声をよく聞きます。爽やかで清潔なイメージ、日本人が好むタイプでしょうか。また、石鹸にはいろいろな機能がありますが、やはり「香り」が一番重要ということかもしれません。「疲れて家に帰り、シャワーで使う石鹸の香りにとても癒される」と言った男性もいます。彼にとって、香りの癒しの体験は、石鹸の香りに始まったということでしょうか。
「石鹸」、「洗濯」の歴史は、メソポタミアのシュメール遺跡から出土した粘土板に、石鹸の使用、製造法が楔形文字で記され、最も古い記録とされています(イスタンブール考古学博物館蔵)。ポンペイの遺跡からは洗濯所のような施設が発掘され、足で踏むなどの物理的行為で汚れを落としたり、植物性のアルカリ(灰汁)や尿などを洗浄剤として用いていた様子を想定することができます。
その後、獣脂と木灰を原料とした現在の石鹸の原形が誕生し、8世紀にはイタリア、スペインなど地中海沿岸の地域で、オリーブ油と海藻灰ソーダを原料とする硬い石鹸が作られるようになりました。その後、南仏マルセイユ周辺が、質のよい石鹸製造の中心地となり、マルセイユソープとして、その伝統は名前にも残り、今なお受け継がれています。
日本はどうでしょう? 江戸時代の庶民の生活では、洗顔には小豆の粉や米ぬか、衣類の洗濯にはムクロジやサイカチなどの植物が使われたと言います。これらの植物にはサポニンという成分が含まれ、界面活性剤となり、水では洗い流せない脂性の汚れを、水に溶かすことができます。石鹸について最も古い文献では、16世紀、石田三成が豪商に送った礼状に「しゃぼん」の文字があります。江戸時代の蘭学者の本にも記載があり、当時の石鹸は薬として扱われる医薬品でした。

|
織田信長や徳川家康も石鹸を使ったというのが定説ですが、明治時代まで石鹸は高級品であり、輸入品のみ、さらには品質もまばらという状況で、庶民の手の届くものではありませんでした。
幕末の開国以来、貿易が本格的に再開し、科学技術等の情報も盛んに入り、石鹸の輸入量も右肩上がりに増える中、石鹸製造の国産化を計ろうという動きも出てきました。その中の一人が、1873年、横浜で石鹸製造所を開業した堤磯右衛門(つつみ いそえもん)氏です。フランスの写真師ボイル氏から石鹸の効用と製造法を教わり、試行錯誤を重ね製造に成功し、製造所の創立に至りました。
その後、紆余曲折を経て、1890年、現在の花王㈱の前身・長瀬商店から「花王石鹸」が誕生します。この頃から庶民の手にも届くようになり、また、「石鹸」というものを知ってもらうため、盛んに広告も出されたようです。堤石鹸製造場の原料リストには、香料として白檀(びゃくだん)油、丁子(ちょうじ)油、山椒(さんしょう)油、樟脳(しょうのう)油の記載があります。
私たちが楽しむ手作り石鹸も然りですが、石鹸製造は化学の世界です。工場の設立や品質の改善、材料となるソーダ灰の製造やグリセリンの回収等々、盛んに取組みが進んだところに明治の日本人の情熱、意欲を感じます。ふだんあたりまえに使っている石鹸は、先人たちの苦労の上にここまでのものになったことを思うと、胸が熱くなります。
*参考文献:『花王石鹸五十年史』小林良正、服部之総 花王石鹸五十年史編纂委員会
*日本の石鹸製造史に興味のある方は、花王ミュージアム(東京都・墨田区)、横浜開港資料館(横浜市・中区)をおすすめします。見学についての詳細は、各施設に直接お問い合わせください。
https://www.kao.com/jp/corporate/outline/tour/kao-museum/
http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

当時使われた金型などが展示されている。 |

繊細なデザインで完成度はかなり高い。 玉の肌石鹸(株)製造。 |
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。