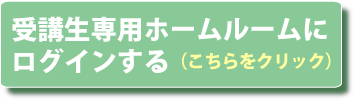ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.63
森林浴のすすめ
新緑のまぶしい季節です。この時期は植物の生命力あふれる香りを、存分に楽しみたいものです。「森林浴」という言葉があります。これは1982年に当時の林野庁長官・秋山智英氏が考えた造語で、「海水浴」や「日光浴」という言葉になぞらえ、森の香りを浴びて心身を整えることが提唱されました。以来、森に入ると気分がよくなるのは、森の木々が発する物質「フィトンチッド」によるもの、自然の樹木の香りの効果はイメージ的なものでなく、科学的なものであることが、理論的に認知されるようになりました。
自然療法が保険制度に組み込まれているドイツでは、適応される療法についての研究も盛んで、温泉療法、水療法など歴史も古く、データも集積されています。その中のひとつに森林療法もあり、温泉と森を組み合わせた保養リゾートなどもあるようです。
国土の7割を森林が占める森林大国の日本に暮らす私たちにとって、森や林、木々はとてもなじみがあります。だからこそ「森林浴」という言葉もスッと受け入れられたのではないでしょうか。2003年には「森林セラピー」という言葉が誕生し、高まるストレス社会に、森林の癒し効果が注目を集めました。森林浴を英語で何というか、実はとても困った経験があります。直訳すると「Forest bathing」ですが、これは日本人が作った英語だそうで、海外では通じにくいようです。タスマニア島で森林の研究者に会った際も、私の英語の拙さもありますが、説明に苦労しました。最近ではむしろ「shinrin yoku」だそうです。

森を上から眺められる公園がある。 |
アロマテラピーを説明する時にも「森林浴もアロマテラピーです」と言うとわかりやすかったりするので、よく例に使いましたが、森林浴は植物が生み出すフィトンチッドを体内に取り込むことで、心身の健康に役立てるものです。「森の香り」の代表には、マツ、ヒノキ、スギの枝葉などに含まれるα(アルファ)-ピネン、マツやモミに含まれる酢酸ボルニルなどがあり、集中力を高めたり、また集中を解きほぐす効果があったり、入眠を促進するというデータがあります。また、コウヤマキ、スギ、ヒバ、ヒノキなどの木部に含まれるセドロールという成分には睡眠の質を高めるという報告もあります。森を歩くこととアロマテラピーとして樹木の精油を楽しむことは、共通の効果があると考えてよいでしょう。

|
森の中を歩くことの効果は香りだけでなく、鳥のさえずりを聴いたり、木漏れ日を浴びたり、清々しい空気を深呼吸したり、五感を潤すたくさんの効果を同時に得ることも出来ます。外気の中で鼻をクンクンさせることは、嗅覚トレーニングの効果も期待できます。天候、湿度によって、香りに対する自分の感じ方が変わることに気づいたり、小さな発見がたくさんあるでしょう。精油の香りとその原料植物の香りの違いを感じることも出来ます。見回せば、森とはいかずとも公園や神社など木々の茂る空間は意外とあります。さあ、お出かけしましょう。

このエリアには広葉樹が集まり、種類も豊富。 葉の形、樹形、緑の色も異なり、森の豊かさを感じられる。 |
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。