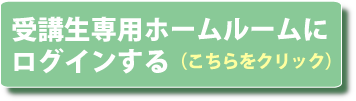ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.60
戦国武将と香り
日本の香り文化は「淡路島に香木が流れ着いた」という日本書紀の伝説に始まります。飛鳥時代、仏教の伝来と共に中国から香木が伝わりました。沈香(じんこう)などの樹木です。沈香はジンチョウゲ科のジンコウジュという常緑高木にその樹脂が沈着したもので、東南アジア、インドなどが原産です。極めて稀少で、大変高価なものでした。
香木は薬としても重要なもので、香薬とも呼ばれました。平安時代には、貴族たちの間でこの希少な香木を粉末状にし、丁子(ちょうじ)など他の香薬と調合した「練香(ねりこう)」が楽しまれるようになります。仏教寺院での供香(そなえこう)のみならず、室内に香りを燻らせたり、衣服に焚き染めたりと、貴族たちの生活の場でも親しまれるように広がりました。

|
時代が貴族社会から武士の社会へ移ると、香の文化は武士たちにも受け継がれ、武士のたしなみとして親しまれるようになります。茶の湯同様、禅との関わりで愛好され、戦の前の気持ちを鎮めるためであったり、香りの精神性が重用視されるようになります。特に沈香が好まれ、上級武士や僧侶の間では沈香一木を焚く手法も盛んになって行きました。
奈良の正倉院の宝物殿には、胡椒(こしょう)、麝香(じゃこう)、ヒハツ、丁香(ちょうこう:丁子のこと)などの香薬と共に「蘭奢待(らんじゃたい)」と呼ばれる黄熟香(おうじゅくこう)が納められています。黄熟香とは沈香の1種で、長さ156㎝、重さ11.6㎏、香木としては大変巨大なものです。蘭奢待がいつ頃正倉院にやって来たのか、どこから入手したものかなど、多くの神秘にあふれていますが、室町時代には天下の名香という扱いでした。
現在の蘭奢待には将軍足利義政、織田信長、明治天皇が切り取った痕が記され、東大寺にも明確に記録が残されています。正倉院には他にも宝物があるにもかかわらず、香木が注目されていることで、当時いかに羨望を集める存在であったかがわかります。
蘭奢待に限らず、香木は時の権力者たちにより、富や財力の象徴として競って誇示されました。戦国時代の武将たちは、天皇への献上品として大量の香木を贈った記録も残され、切り取られた正倉院の蘭奢待も、義政も信長も半分は天皇に献上しています。旧約聖書にあるシバの女王がソロモン王に乳香などの香料を大量に贈ったエピソードに共通しますね。

|
徳川家康も例外ではなく、熱心な香木コレクターだったようで、その一部が久能山東照宮などに残されています。家康自身、自ら練香を調合し、「香之覚(こうのおぼえ)」という自筆の書が残されています。香は「千年菊方(せんねんきくほう)」と命名され、寿福長命の薫物として平安時代から継承される「菊花」にちなんでいます。香之覚は水戸の徳川ミュージアムに現存し、今年は公開されています。
戦国時代から江戸時代の初期にかけ、武士には「かくあるべし」という美学があったようで、その中のひとつに髪に香を焚きしめることが身だしなみとしてあったそうです。常に死と背中合わせの武士の世界で、身繕いを整えることは、必死の決意を示すことでもあったようです。香りにひそむ精神性を戦国武将たちに学ぶ思いです。

焚くと沈香ベースのふくよかな香りが漂います。 |

ワークショップに参加しました。 粉末にした複数の香料に蜂蜜などを加え 練り合わせるのは、力の要る作業です。 |
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。