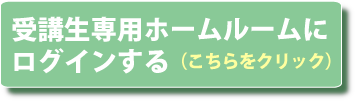ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.59
干支とハーブ
今年は卯年。ウサギにちなんだハーブというと「西洋ウサギギク」=アルニカ Arnica montana があります。あまりなじみはないかもしれませんが、日本でも高地に自生するウサギギクの仲間です。同様に山岳地帯の草原に自生し、12世紀の薬草療法の書物に記載があります。
厳しい山風にも負けない強靭なハーブで、花には150種類以上もの薬学的に有用な成分が含まれ、18世紀には痛風、リウマチ、静脈瘤、静脈炎などの治療薬として使用されていました。葉のつき方がウサギの耳に似ているので、この名がついたようです。
皮膚刺激の強い成分を含むため、使い方には注意が必要とされますが、アルコール等で抽出したエキスや浸出油が、打撲などをやわらげるクリームなどに使われています。

|
植物ではありませんが、ハーブを知るに極めて欠かせない存在が、ビアトリクス・ポター作の童話『ピーターラビット』シリーズでしょうか。この童話には、カモマイルやラベンダーが登場し、食べすぎたピーターのお腹を労わったり、ラベンダー煙草でリラックスしたり、と英国の日常にはハーブが寄り添っていることを匂わせてくれました。
レタスを食べて眠くなるというシーンについても賛否両論ですが、ここで言うレタスはおそらくワイルドレタスだったと思いますし、最近ではレタスの白い乳液が害虫を遠ざけるという研究が報告され、ポター女史が食材としてだけでない野菜の可能性を示唆してくれているようにも見受けられます。
話はウサギから離れますが、最近よく耳にする生薬が「女貞子(ジョテイシ/ニョテイシ)」です。こちらも聞きなれない名ですが、実はとても身近にある庭木、「ネズミモチ」です。生垣、街路樹などにも使われ、誰にも記憶に残る植物かもしれません。
夏頃に咲く花に強い香りがあり、その匂いに印象を持つ方も多いと思います。秋に紫黒色、楕円形の果実を結び、この実がネズミの糞に、葉はモチノキに似ているため、この名がついたと言われます。
正確には中国原産で近縁の「トウネズミモチ」の果実を乾燥させたものが女貞子ですが、成分は共通のものを含むため、ネズミモチにも同様の効果があるとされています。伝統的には滋養強壮、白髪予防、筋力低下改善、視力減退改善、利尿作用と幅広く使われ、骨粗しょう症の抑制に対する研究論文もあるようです。果実を煎じたり、冬至の頃にホワイトリカーに浸けて薬用酒を作ることができます。

|
身近に見かける植物にこんなに多くの効用があるのは驚きです。ちょっとしたきっかけで調べてみると、新たな発見があり、視野が広がることが多々あります。今年も好奇心の目をイキイキと働かせていきたいと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。