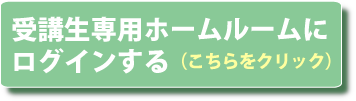ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.54
ラベンダーの風に吹かれて2022
記録的な猛暑が続き、熱中症には至らずとも、疲れやすかったり、おなかの調子がくずれたり、頭痛がしたりという、いわゆる「夏バテ」症状を感じている方は多いのではないでしょうか。このメルマガの6月号(vol.52)でも取り上げましたが、夏バテは脳と自律神経の働きが大いに関わっています。暑さに対応すべく自律神経は大忙し、それをコントロールする脳もかなり疲弊しています。脳を労わるための栄養補給と睡眠、そして脳が喜ぶ楽しいと感じる時間を積極的に作ることも、夏は必須かもしれません。夏休みはこれからという方は、ぜひ、楽しんでください。
7月中旬、北海道・富良野の夏を4年ぶりに訪れました。7月中旬と言えばラベンダーの最盛期、各地でラベンダー祭りが開催され、観光客も一番多い時期です。広大なラベンダー畑が、その日はやや強いぐらいでしたが爽やかな風に煽られ、まさにラベンダーの海のようです。最盛期のラベンダーのフレッシュな香り、格別であることを再認識しました。

(中富良野Nanakaの花畑) |

今年はラベンダー畑のライトアップで賑わいました。 初めて見る幻想的な光景です。 |
富良野エリアのラベンダー畑は、今は観光用のところもありますが、元々は香料生産のための農地でした。ラベンダー生産最盛期の栽培面積は、その後観光ブームとなった1980~90年代の比ではなく、富良野沿線でも約210ha(東京ドーム45個相当)あったそうです。日本のラベンダー生産史を辿ってみると、香料と言えば輸入が中心だった1930年代、天然香料の国産化に熱心だった曽田香料㈱の故・曽田政治氏が、フランスより真正ラベンダーの種子を取り寄せたのが始まりです。のち、栽培試験を重ね、適地として選ばれたのが北海道、札幌エリアに自社農場が数カ所設けられました。ラベンダー発祥の地として、今もラベンダーで賑わっている所もあります。太平洋戦争を挟み、日本中の農地は荒れつくし、ラベンダーも同様でした。生産意欲も荒む中、ラベンダーに魅せられ立ち上がったのが、上富良野町の農家のグループでした。委託栽培がスタートし、蒸留所も建設され、富良野エリアのラベンダー精油生産の始まりです。
「ようてい」「おかむらさき」「はなもいわ」、真正ラベンダーの北海道産優良品種です。ラベンダー精油の品質は、エステル成分含有量で評価されることが多いですが、この3品種は本家フランス産を上回りました。これに「濃紫3号」が加わった4種が今なお、富良野エリアの夏を彩ります。おかむらさきは想像つきますが、他の2種は道民以外にはなじみなく、私も不思議に思っていましたが、「羊蹄山」のようてい、はなもいわは「花+藻岩山」、まさに北海道の風景が浮かんでくる素晴らしい命名です。
お土産におかむらさきを刈らせていただきました。わが家でドライになって、心地よい香りを漂わせてくれています。今年の記念としてバンドルズに仕上げ、手元に置きたいと思います。ラベンダーの香りと共に、刈り取らせていただいたNanakaの花畑さんの想い出はずっと香ることでしょう。

|
*補足情報: 日本のラベンダー史について興味をお持ちの方は、佐々木薫先生がゼネラルマネージャーを務める「(株)生活の木」の公式スマホアプリ内の連載記事「佐々木薫 ハーブ紀行」の中で、日本のラベンダー史について詳しく解説をしていますので、こちらをご覧ください。※スマホアプリ限定です。パソコンからはご覧いただけません。
treeoflife-app:/tab/atom/440c2210?page_id=01FTSJ25NVDWYXD85V0KHZ7Q17&type=basic
※「佐々木薫 ハーブ紀行」の閲覧には生活の木公式アプリ(スマホ専用)のインストールが必要です。お持ちでない方は下記から無料でダウンロードいただけます。
URL:https://yappli.plus/treeoflife_lp
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。