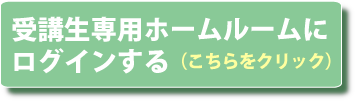ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.51
リンデンの花香る季節、プルースト効果
新緑のまぶしい季節です。この時期はできるだけ外に出て、風が運ぶ自然の植物の香りを感じたいものです。日常のふとした時に遭遇する香りに、瞬時にして、過去の思わぬ時代、空間に引き戻されることがあります。同時にその時に感じた感情までが蘇ってくる、その現象は「プルースト現象」と呼ばれています。フランスの長編小説、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の中で、紅茶に浸したマドレーヌの味と香りから、一瞬にして子供の頃の記憶がよみがえるシーンがあり、そこから名づけられたものです。口にしたのは紅茶でしたが、思い出されたのは紅茶と同じように飲んでいた菩提樹のお茶の香りでした。フランスでは、母が子供へおやつに菩提樹=リンデンのお茶を淹れる、リンデンティーは家庭の味だということもうかがえます。

|
菩提樹と言えば、シューベルトの「泉に添いて 茂る菩提樹」という歌曲からその名を知った人も多いと思います。ここで言う菩提樹は、ナツボダイジュとフユボダイジュの交配種、西洋ボダイジュ=リンデンを指します。ヨーロッパの人たちはこの木が大好きで、街路樹やシンボルツリーとして植えられています。リンデンは葉も花も実も姿も、すべてがやわらかく、甘く、心地よいのです。フランス語ではティユール(Tilleul)と言い、プロヴァンスのビュイ・レ・バロニーという町が産地です。かつては年1回、この村でリンデン市が開かれ、ヨーロッパ中の薬草問屋やハーブティーメーカーが集まりました。

プロヴァンスのリンデン市 |
現在の主な用途は、花と苞を薬草茶として用いますが、木部はやわらかく加工しやすい為、楽器や工芸品に使われます。また樹皮からは繊維が採れ、ロープの原料となりました。
薬草として使われるようになったのは、リンデンの歴史の中では比較的新しいことのようです。開花期には甘い香りが漂い、ミツバチが集まります。
日本の固有種「シナノキ」はリンデンの近縁種です。北海道から九州までの山地に分布しますが、特になじみがあるのは北海道と長野県です。北海道ではアイヌの人たちが、この木から採る繊維で衣服などを織りました。一方、長野市では「市の木」として制定されています。長野県を示す「信濃(シナノ)」という地名は古事記にも登場し、シナノキがたくさん生育していたからという説があります。倉科、仁科、蓼科と、「シナ」のつく地名はたくさんあります。シナノキの花も甘い香りがし、蜜源植物です。

リンデンの木をよく見かけます |
花からは精油も抽出され、気品のある芳香です。国内でも街路樹としてシナノキを植栽するところがあります。開花期の芳香、そして青々とハート形の葉が茂る様子は、大変美しい木洩れ日を作ります。生活の木のハーブ園「薬香草園」には設立時(1996年)に植えた3本のリンデンの木があり、5月頃から蕾をつけ始め、5月下旬から6月にかけ、開花します。今年もたくさん咲いてくれることを祈ります。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。