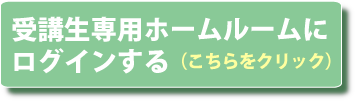ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.48
春を告げる香り、ミモザ
暦の上では立春を迎えました。しかし、寒さは一層厳しくなり、北陸、東北、北海道、北国から届く、今年の豪雪のニュースには胸が痛みます。謹んでお見舞い申し上げます。一方、フラワーショップの店頭には、スイートピー、ストック、チューリップなど春の花が並び、ヒヤシンス、ムスカリなどの球根植物も顔を出しています。道を歩けば、水仙や蝋梅の香りがどこからともなく漂って来たり、季節を香りで感じられることのありがたさを実感します。
フランスで春を感じる花というと、ミモザだそうです。地中海沿岸にはミモザの自生する「ミモザ街道」と呼ばれるルートがあったり、3月8日は「ミモザの日」とされ、ミモザの花を贈る習慣があります。ミモザ街道の村では、「ミモザ祭り」も開かれます。黄色いフワフワとした小さな花は、まさに春の妖精のようで、春の到来を盛り立てます。

|
最近は、日本でもミモザの人気が高まり、フレッシュの花やドライフラワーのリースが店頭にも並ぶようになりました。花より先に、カクテルの「ミモザ」や「ミモザサラダ」に出会う人も多く、ミモザとはサラダの種類だと勘違いされた笑い話もあります。確かにサラダですが、ゆで卵の黄身を細かく散らし、ミモザの花に見立て、その名が付きました。卵サラダよりミモザサラダの方が、一段と魅力的ですね。

|
「ミモザ」とは、実は正式な植物名でなく、通称または一般名称です。ミモザと呼ばれる品種は、多数あるようです。アカシア属で、学名はAcacia dealbata(フサアカシア)。その他、シンジュバアカシア、ギンヨウアカシアなどがあります。オーストラリア、アフリカ原産、マメ科の常緑性高木です。ミモザという名前がどこからついたのか、諸説ありますが、花が「オジギソウ」に似ているため、そう呼ばれるようになったと言われます。オジギソウの学名は、Mimosa pudicaです。

|
外観もとてもかわいいですが、一番の魅力は、香りでしょう。香りが弱い品種もあったり、採れる量も少なく、フレグランスや石鹸には合成香料が使われており、天然の香りを知る人は少ないかもしれません。園芸店に苗が並び、庭木として植える方も増えていますが、残念なことにその多くは、香りはあまり期待できません。
切り花として出回りますが、香料を採るためにも生産されます。ミモザの香りは繊細なため、水蒸気蒸留ではなく、有機溶剤抽出法で採油されます。一般に出回るのはアブソリュートです。大変粘性が高く、5~25%に希釈されたものが使いやすいでしょう。香りを言葉で表現するのは難しいですが、オレンジの花、ライラックの花、グリーン調、アニス様、これらをあわせ持った香りです。
私自身は一番と言ってよいぐらい、花もその香りも好きですが、好みははっきり分かれるようです。香りの引き出し、香りの経験はたくさんあったほうがよいようです。この春は、ミモザの香り、ぜひご体験ください。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。