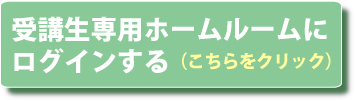ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.45
ユズ香る季節到来、ユズの産地を訪ねて
日本は世界に誇る柑橘王国だそうです。秋の味覚にはスダチやカボスを存分に楽しまれた方も多いと思います。庭木として植えていらっしゃる方も多いと思いますが、私も友人の収穫のお裾分けに預かり、スダチをたくさんいただき、シラスと合わせてパスタにするなどして楽しみました。
さて、次は? というとユズではないでしょうか。国内一の生産量を誇るのが、高知県で、11月初旬から収穫が始まります。今年はちょうどその時期に産地の馬路村(うまじむら)を訪問することがかないました。ユズといえば食卓を彩る調味料ですが、冬至のユズ湯もおなじみです。冬至は昼間の時間が最も短い日、古くは新しい年を迎える日でした。この日にユズ湯に入るのは、いろいろな説もありますが、厄払いのための「禊(みそぎ)」の意味合いが強いようです。冬が旬の柑橘の中でもユズは香りが強く、「強い香り=邪気を払う」という考えから、ユズ湯が習慣になったのではないでしょうか。また、ユズは実がなるまでに17~18年という長い年月がかかるため、長年の苦労が実るようにという願いも込められるといわれます。

|
ユズの精油は果皮に含まれ、血行を促進し肩こりや冷え性を緩和したり、体を温め、風邪を予防する効果があります。湯船にユズの果実を浮かべることはあっても、香りがどこにあるのか、効果は何にあるのかは、意外に知られていないこともあるようです。果肉や果汁より果皮が大事なので、果皮だけを削り取って使うのが効果的です。生のまま、もしくは果皮を乾燥させて保存することもできます。また、ユズのパワーは種子にもあり、アルコールに漬けてエキスを抽出し、希釈してローションになります。また、種子からオイルも採れます。

|
ユズの精油は意外に採油量が少なく、大変酸化しやすいという難点があります。それゆえ価格も高価です。ユズの香りの効果を楽しむには、果皮をパウダー状にしたものなどを使うのがおすすめです。たとえば、カカトのケアのためのボディスクラブです。ミキサーなどで細かくパウダー状にした天然塩大さじ2とアーモンド油大さじ1を混ぜ、なめらかになるまでよく練ります。そこにユズパウダーを小さじ1加え、さらに混ぜます。これを少量ずつ手にとり、小さな円を描くようにかかとをマッサージします。事前に足浴または入浴で足にたっぷり水分を含ませ、皮膚をやわらかくしておきましょう。いずれもやさしく少しずつ、1日おき程度に続けることがポイントです。ケアしたあとは、保湿クリームをぬり、木綿または絹の靴下をはいて寝れば万全です。
精油も果皮も光毒性があり、皮膚刺激は強い方です。使いすぎにはご注意を。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。