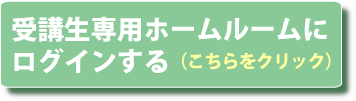ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.40
日本の森を育むアロマ
日本は、国土(3,779万ha)の約7割を森林が占める、世界有数の森林国です。森林には原生林、自然に育った苗を利用して作られた天然林、目的にあわせ人が作った人工林があります。人工林で育った木は収穫され、切ったあとはまた苗木を植え、森林に育てます。人工林には、スギ、ヒノキ、カラマツ、アカマツ、トドマツなど、成長が早く、建材に適した針葉樹が多く植えられます。 人が全く立ち入らず、自然状態で長期安定している森林が「原生林」。原生林には多様な生物が生存し、豊かな生態系が残っており、屋久島や小笠原諸島、白神山地、知床など、世界遺産の原生林として有名です。

|
天然林、人工林には「日本三大美林」と称される林があります。天然林が、木曽ヒノキ、秋田スギ、青森ヒバ、人工林は、天竜スギ、吉野スギ、尾鷲(おわせ)ヒノキです。「ヒバ」「スギ」「ヒノキ」、いずれからも採油が行われ、私たちには和精油としておなじみです。精油を得るために植林されているというより、植林された木の活用のひとつとして採油が行われています。精油の原料植物として捉えると、何気なく眺める山の景色も、ぐっと親しみがわいて来ます。
人工林では、植栽した木を間引きして密度を調整する「間伐(かんばつ)」といった手入れがなされます。木立の間に日光を入れ、下草を生やし、土壌を育成し、土砂崩れを防ぎます。適切な伐採を行わないと、新しい木が植えられず、高齢の木々ばかりとなり、二酸化炭素の吸収量が低下するなど、森林の持つ多面的機能の低下にもつながります。人工林をいきいきさせるためには、「植林」「間伐」「伐採」「利用」というサイクルを回すことが重要です。それには木材の需要を増やすこと、また、間伐材の用途を広げることなどが必要です。ヒバ、スギ、ヒノキなど木部から抽出する精油は、間伐材から得られ、またモミなどは、伐採して木材として加工される木から落とされた、枝葉を活用します。豊かな森をつくる林業のサイクルの中で、微力ながら、精油を得ることも、大きく貢献していると言ってよいのではないでしょうか。

木部以外に枝葉から精油を抽出することもあります。 |
もちろん、アロマテラピーとして活用することも重要です。ヒバ、ヒノキ、スギは、江戸時代から植林されて来た歴史があり、殺菌力、耐湿性、強健さが建材として評価されています。ヒノキのまな板や風呂桶、スギのお弁当箱など、高級品として存在し、その有用性も身近に感じる機会がたくさんあります。精油を利用する際も、そんな背景はとても参考になります。また、産地をはじめ各地域に伝説や活用の習慣があり、それを聞き集めるのも楽しい作業です。

日本一長い木造の橋ですが、樹齢150年以上の青森ヒバの木が使われています。 丈夫で、腐らないことが理由でしょうか。 |
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。