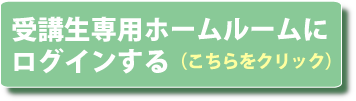ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.38
日本のハーバルライフ
門松、お屠蘇、七草粥、節分など、年頭から2月にかけての季節の行事には、それぞれにハーブ(薬草)が登場し、日本人の生活にハーブがなじみあるものであることをあらためて実感します。
唐時代の中国では、暦の中で奇数の重なる日は「陰」とされ、陰の邪気を払うために、季節の旬の植物から生命力をもらう行事が行われました。季節の変わり目を「節」と言い、それらの習慣が、奈良時代、日本に伝わり、五節句として定着しました。例えば、3月3日「上巳(じょうし)の節句」の邪気を払う植物は「桃」です。ひな祭りに桃の花を飾るのはおなじみですが、中国ではその実が不老長寿の果実とされ、日本神話にも登場します。種と花は生薬であり、民間でも使われて来ました。夏の土用に桃の葉の湯に入る習慣は、江戸時代からあったようです。あせもや湿疹など肌のトラブルを防ぐと言われます。

|
日本の薬草療法というと漢方薬が浮かびます。「漢方」は中国のもののような印象を受けますが、5、6世紀に伝わった中国医学が、室町時代以降、日本独自の発展を遂げ、日本の風土や気候、日本人の体質や生活習慣に合った医学に進化しました。「漢方」という言葉は、江戸時代に入ってきた「オランダ医学=蘭方」に対してつけられた日本独自の呼び方です。漢方薬は、原則として2種類以上の生薬を決まった処方のもと作られるもので、用法用量も細かく定められ、医薬品として厚生労働省に認められています。古くから使われ、なじみはありますが、基本は中医学であり、誰もが勝手に出来ることではありません。

|
漢方薬に対し、ゲンノショウコ、センブリ、カキドオシといった、主に単独で、昔から経験的に使われてきた薬草が、民間薬です。家庭で治せる範囲のケガや病気に用いられ、使い方に医学的な背景はありませんが、先人から受け継がれてきたもの、その土地に古くから根付いている生活の知恵であり、健康増進が目的です。例えばドクダミの生薬名は「十薬(じゅうやく)」、「五物解毒湯(ごもつげどくとう)」の処方に入り、漢方薬として使われますが、お茶や入浴剤など、民間薬として単独でも用いられます。神話「因幡の白兎」にも登場する「ガマ」、修験道の山伏は「キハダ」を用いて薬を作った、など日本のハーブは興味深いエピソードにあふれ、身近な植物が魅力あふれるハーブとして迫って来ます。その土地では誰もが知っているような植物で、古くから使い続けられ、さらには似たような近縁種が、地域、民族、宗教などを越えて活用されている、そんなハーブには親しみがあり、信頼性があります。現代の生活環境では、身近に自生する植物を探したり、自分で採取したりするのは難しいかもしれませんが、幸いにも七草粥セットのように店頭に並ぶものもあります。五節句をはじめとした四季おりおりのハーブ使いが季節を感じさせ、日本人の感性の豊かさを実感させてくれます。伝えて行きたい大事な文化ですね。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。