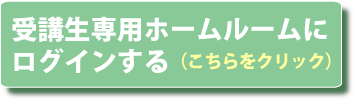ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.37
ポプリの香に寿ぐ
あるキャンドルメーカーのクリスマスギフトに、フルーツポマンダーがセットされていました。フランスの職人が作っているとか。ポマンダーは前回ご紹介した通りですが、その完成品が商品として販売されているのは初めて見ました。ご縁を感じると共に、フランス人にとっても、伝統的なフレグランス小物であることを実感しました。
伝統的な香りの楽しみと言えば、外せないのは「ポプリ」でしょう。私がハーブと出会ったのも、きっかけは熊井明子氏の紹介するポプリからです。ポプリとは、フランス語のpot-pourriが語源で、「腐った壺」というような意味もあります。つまり、何かを混ぜ合わせて熟成させたものという意味です。英語でもそのままポプリと呼ばれ、今やポプリと言えば、室内などを香らせることを目的に、バラなど香りのよい花やハーブ、スパイスを香料と混ぜて熟成させたものを指します。かつては女子のバイブル的小説だった「赤毛のアン」シリーズにも登場し、そこでこの言葉を見つけ、どんなものなのか空想の羽を広げた女性も多くいました。そこでは「雑香」と訳され、想像力を働かせて作ってみた方もいらっしゃいました。それほど女性を惹きつける魅力があったということでしょうか。

|
ポプリの源流をたどると、古代エジプト時代に香として焚かれた「キフィ」にたどり着きます。香りのよいハーブやスパイス、樹脂などを練り合わせて作ったもので、ワインや山羊のミルクなどもつなぎとして使われました。実際、ポプリには何か決まった形があるわけではなく、生活の中に香りをとり入れることは、それぞれの時代、それぞれの地で行われて来たのではないかと思います。それが、現在私たちが知っているポプリに近い形で広く親しまれたのが、16世紀、英国のエリザベスⅠ世の時代です。宮廷に専用の部屋が設けられ、庭園の花やハーブを乾かし、ポプリやサシェが作られたと言います。女王自身も香りを大変好み、その流行は貴族の間から一般まで広がっていたようです。

|
ポプリは、完全に乾燥した花、ハーブ、スパイス、木の皮、樹脂、精油などを混ぜて作るのが一般的ですが、半乾きの花を粗塩に漬けて熟成させたものにハーブやスパイスを加えるモイストポプリもあります。後者の方が香りはより濃厚で、英国の古いお屋敷に香っていそうなクラシックなイメージです。使う素材にルールはありませんので、庭にある植物を自分で乾かして作るのもよいですし、いただいた花束をポプリにするのもよいでしょう。ただ、香りを整えるには、芳香性の高いローズやラベンダー、精油を使います。精油を加える時は直接花につけるのではなく、乳香や、白檀、シナモンなどに浸み込ませて混ぜ合わせます。新しい年に向け、松葉や菊の花を使い、ポプリを作るのも楽しいでしょう。私も試してみようと思います。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。