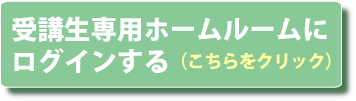ハーブ・アロマ メルマガ 「佐々木薫先生のエッセイ」
vol.34
ハッカの季節
まだまだ続く暑さには、ミントの香りが一服の涼を誘ってくれます。ミントといえばハッカ、日本人にとってハッカは最もなじみのある香りではないでしょうか。ハッカ飴、ハッカ糖、縁日のハッカパイプ等々、幼いころの記憶と結びつき、最もなつかしい香りかもしれません。実は、ハッカは日本が誇る天然香料であり、かつてその生産量が世界市場の7割を占めていた時代もあります。今回は、もうすぐ収穫を迎える、知ってるようで知らない、ハッカの世界をご紹介しましょう。

|
ハッカは、シソ科の多年草「和ハッカ(日本ハッカ)Mentha arvensis」の地上部を水蒸気蒸留して得られる精油(香料)です。ペパーミント(Mentha piperita)やスペアミント(Mentha spicata)もハッカの近縁種ですが、香りや形状、精油成分の違いにより、区別されています。Mentha属は世界中に140種以上あると言われ、交雑しやすく、正確に分類が難しい植物です。精油は「和種ハッカ」という名がついていますが、総メントール量を規定以上含む和ハッカ精油がそう呼ばれています。ペパーミントなどに比べ、ツンと鼻をつく香りが強いのが特徴です。
現在の産地は、北海道・滝上町を中心とした北見地方です。精油生産のための収穫は、花穂が立ち上がり3分の1ほど花をつけた頃。その頃が葉の香りも最も香り高く、花を含め、地上部全体を刈り取ります。収穫後、1カ月ほど乾燥させ、蒸留を行います。例年、収穫は秋風が立ち始める8月下旬、蒸留は9月の下旬頃です。現在、ここで栽培されているハッカは精油生産用で、収穫、蒸留は年に1時期のみ、大変貴重な精油です。ハッカはもともと中国原産で、生薬として漢方薬にも使われています。日本へは江戸時代に入り、19世紀以降、「薄荷脳」生産を目的に栽培されました。薄荷脳とは和種ハッカのメントール成分を結晶化させたものです。

|
メントールには、局所を刺激し、知覚をマヒさせる作用があります。和種ハッカ精油は鎮痛やかゆみ止めとしての効果が期待できます。アロマスプレーを作り携帯すると、アウトドアで役立つでしょう。スーッとする清涼感ある香りが、胃粘膜を刺激し、消化管の運動を促します。私は、胃がもたれた時、乗り物酔いなど消化器系のトラブルのケアに、バッグの中に常備しています。ハンカチに1滴落とし、香りを嗅いで救われたことがしばしばあります。ただし、刺激が強いので、使用する量には要注意です。

|
北見市には「北見ハッカ記念館」があり、ハッカ産業の歴史が保存されています。館の周囲には「まんよう」「ほくと」といった、北見で改良された優良品種が植えられ、生のハッカの香りも体感できます。興味のある方はぜひ、お訪ね下さい。
日本園芸協会 指導部 佐々木薫
◎このメルマガの文章・写真の転載を禁じます。